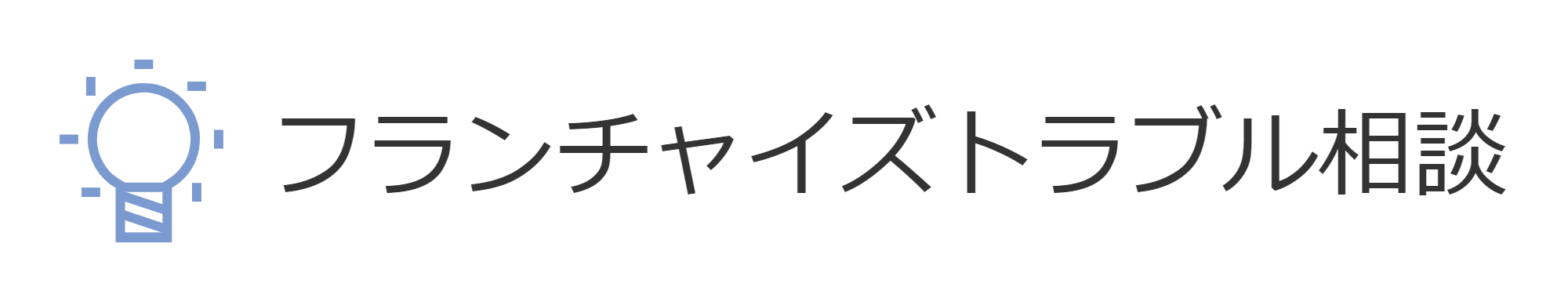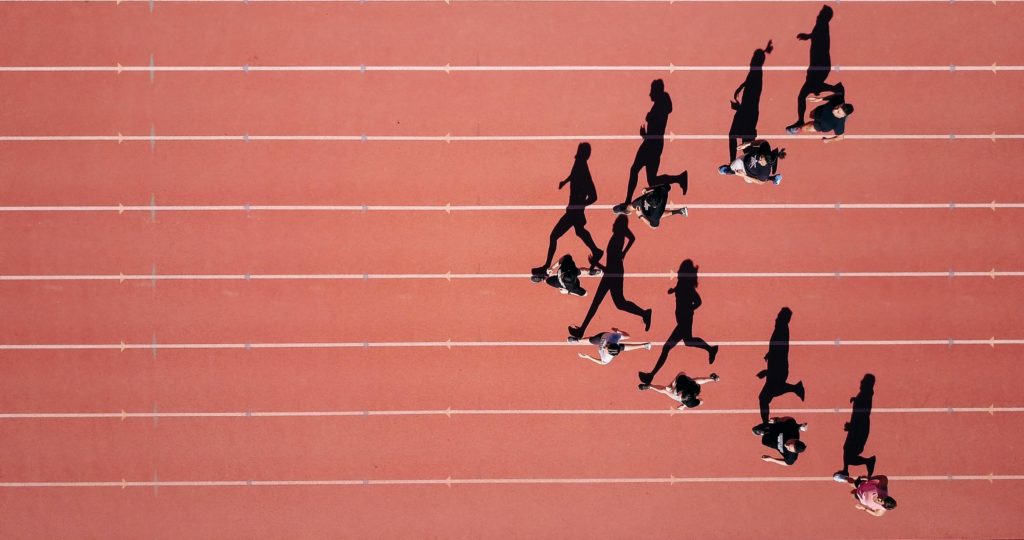学習塾のフランチャイズに加盟しているのですが、フランチャイズ本部に対して色々不満があり、このままフランチャイズに加盟しているメリットが感じられません。フランチャイズを脱退して、自分の名前で学習塾事業を始めたいと考えていますが、どのような方法で行えばよいでしょうか。
フランチャイズの脱退・解約方法
加盟店が、フランチャイズ契約を締結したものの、様々な理由により脱退・解約したいと考える場合があります。
フランチャイズ契約を終了させる方法としては、大きく分けて
- 契約期間満了により契約を終了させる場合(契約の不更新)
- 契約期間途中で契約を終了させる場合
とに分けることができます。
期間満了により契約を終了させる場合
フランチャイズ契約においては、多くの場合、契約期間が定められています。その契約期間が満了することによって契約は終了します。
本来であれば、単に契約期間が満了しさえすれば、特段何も行動を起こさなくても、自動的に契約は終了することになります。
もっとも、通常のフランチャイズ契約においては「契約期間満了の●ヶ月前に契約を更新しない旨の通知を行わない場合には、契約は自動的に更新される」といった内容の自動更新条項が定められています。
つまり、「更新をしない」という通知を期限内に行わないと、契約が更新されてしまい、継続することとなってしまうのです。
そのため、期間満了により契約を終了させたいのであれば、フランチャイズ契約書をよく読んで、契約期間の満了日と、いつまでに不更新を通知をしなければならないのかを確認し、期限に遅れないように通知することが必要です。
不更新の通知は、通常、書面によることが求められている場合がほとんどです。また、もし、書面によることが条項上求められていなくても、後で争いにならないように、内容証明郵便などの書面で明確に通知しておく必要があります。
例えば、次のような文面で通知すれば良いでしょう。
弊社と貴社との間のフランチャイズ契約は、★年★月★日に契約期間が満了となりますが、弊社は、契約を更新致しませんので、その旨ご通知致します。
契約期間途中で契約を終了させる場合
さて、契約期間満了日が近づいているのであれば、上記の方法で契約を終了させれば良いのですが、問題は契約期間満了日がだいぶ先のため、それよりも前に、契約期間途中で契約を終了させたい場合です。
中途解約条項による解除と解約一時金
この場合、まず確認すべきなのは、フランチャイズ契約の中に、加盟店側の都合で期間途中に一方的に解約することを認める「中途解約条項」があるかです。
もし、このような中途解約条項があるのであれば、これに従って契約を終了させることを検討することになります。
もっとも、フランチャイズ本部としては、契約が期間途中で終了すれば、以後、契約期間内に入ってくる予定であったロイヤリティ等も入ってこなくなります。そのため、フランチャイズ契約上、こうした加盟店側からの中途解約が認められている場合でも、違約金や解約一時金など、一定の金銭の支払いを条件としている場合が少なくありません。
こうした違約金の支払いに納得がいくのであれば問題ないのですが、加盟店としては契約を終了せざるをえなくなった原因がフランチャイズ本部の側にあると考えているような場合には、とても納得がいかないというケースも多いでしょう。
解約一時金の定めが置かれていたとしても、全ての場合において有効という訳ではありません。解約一時金の定めが、個人の営業の自由や経済活動の自由に対する制限として社会的良識や正常な商慣習に照らして合理的に必要と認められる範囲を超える場合には、その全部又は一部が無効とされることがあります(東京高判平成7年2月27日判決等)。
また、中途解約条項に基づく解除ではなく、次の、債務不履行解除(フランチャイズ本部に何らかの債務不履行があることを理由とする契約解除)や合意解除(フランチャイズ本部との合意により、契約を終了させること)が可能かを検討する策もあります。
その他にクーリングオフが可能かという問題がありますが、この点は「フランチャイズ契約でもクーリングオフはできる?認められた裁判例と注意点」で解説しています。
債務不履行解除
フランチャイズ本部に、フランチャイズ契約上定められた義務の違反(債務不履行)があるという場合には、これを理由に契約を解除することができます。これを債務不履行解除といいます。
債務不履行解除について、フランチャイズ契約上に規定がある場合も、ない場合もありますが、たとえ規定がなくとも、民法の一般原則に基づき解除が可能です。
合意解除
そもそも、契約期間を何年にするかは、フランチャイズ本部と加盟店の合意で決めたものです。
ですから、契約期間満了を待たずに契約を終了させることも、双方が合意しさえすれば、何ら問題なく出来ます。これを合意解除といいます。
通常は、フランチャイズ本部としては、契約が終了してしまえば、契約期間中に入ってくる予定であったロイヤリティ等も入ってこなくなりますし、上述のように、中途解約条項がある場合でも一定の金銭の支払いを条件としている場合が多いことから、無条件に契約を終了させることに合意することは考えがたいところです。
そのため、契約を終了させるとしても、加盟店に対して何らかの金銭の支払い等を求め、これを条件とすることを主張してくることでしょう。
交渉にあたっては、まず、フランチャイズ本部が主張する違約金等について、当然に支払いに応じなければならないものかという検討も重要になってきます。上述のとおり、解約一時金の定めがあっても、それが個人の営業の自由や経済活動の自由に対する制限として社会的良識や正常な商慣習に照らして合理的に必要と認められる範囲を超える場合には、その全部又は一部が無効とされることがあるからです。
また、加盟店としては、フランチャイズ本部に法的責任を問いうるような事情があって、例えば、これによって被った損害について賠償請求が考えられるようなケースであれば、これを材料にしながら交渉することも考えられます。
例えば、加盟時に行われた説明が事実と異なっていたという場合には、情報提供義務違反によりフランチャイズ本部に法的責任が生じる場合があります。この点について詳しくは、フランチャイズ損害賠償|説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法で解説しています。
また、フランチャイズ本部からまともな指導援助がなされてこなかったという場合には、指導援助義務違反も問題となり得ますが、この点は、フランチャイズ本部が何もしてくれない…指導・サポート義務違反が認められるケースとは?で解説しています。
フランチャイズの解約・脱退時に注意すべき点
フランチャイズを解約・脱退した後に、引き続き従前行っていた事業を行うことを考えている場合には、競業避止義務についても注意が必要です。
通常、フランチャイズ契約においては、契約終了後、一定期間については、同じ業種の営業を行うことを禁じる条項が設けられているからです。
したがって、フランチャイズ契約をどのように終了させる場合であっても、この競業避止義務について検討が必要となります。
競業避止義務の問題について詳しくは、【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策で解説しています。
フランチャイズトラブルでお悩みの方へ
フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。
トラブルを未然に防ぐためにも、また発生してしまったトラブルに的確に対応するためにも、早めのご相談が大切です。
フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。
フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事
フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。
▼フランチャイズ損害賠償|説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法
「加盟時にされた説明が不正確だった」という情報提供義務違反の問題について解説しています。
▼フランチャイズの違約金は払わないといけない?拒否できる場合と裁判例を解説
フランチャイズ契約に定められることの多い「違約金」ですが、金額が高すぎるとして公序良俗違反が問題になる場合があります。こうしたケースについて裁判例に基づいて解説しています。
▼フランチャイズ契約と加盟金の返還請求
「加盟金は返還しません」という合意の効力が問題となったケースについて解説しています。