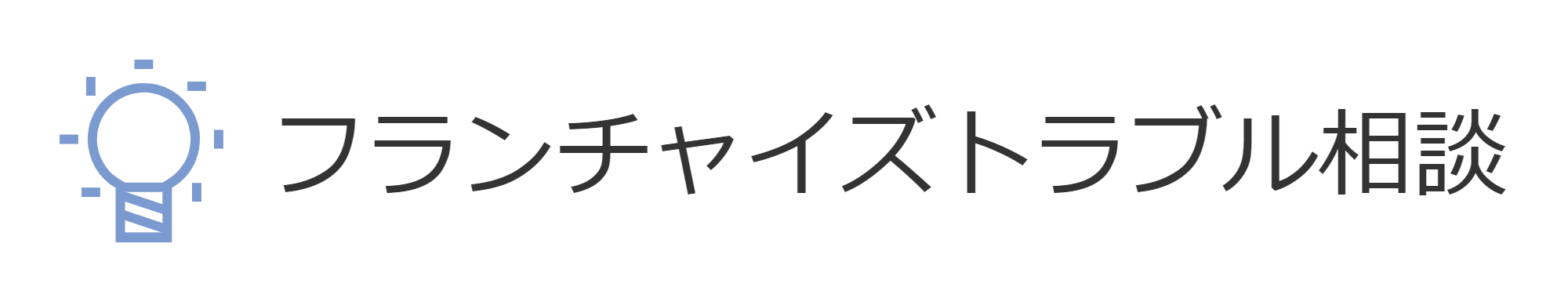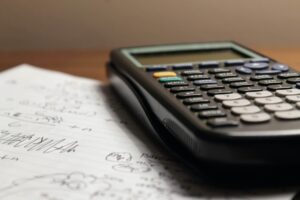フランチャイズ契約書には、フランチャイズ契約の違反があった場合には一定の違約金を支払うべき旨が記載されているケースが多くあります。
支払うべき金額は、特定の金額が記載されている場合もあれば、月額ロイヤリティの何ヶ月分という記載の仕方がされているケースなど様々です。
一見シンプルな条項に見えるため、フランチャイズ契約締結時には簡単に読み飛ばしてしまいがちですが、実際に契約の違反が問題となる場面では、違約金さえ支払えば良いのか、それとも違約金以上の請求を受ける可能性もあるのか、また、契約の違反があれば必ずその金額を支払わなければならないのか、など様々な疑問が湧いてきます。
ここでは、そんな違約金条項の意味について見ていきたいと思います。
違約金とは
違約金とは、契約において、一方当事者に契約の違反があった場合に、他方当事者に対して支払うことがあらかじめ決められた金銭のことを言います。
ただし、実は、違約金の定めといっても、その意味合いは契約によって異なります。
契約違反に対して払うべき「損害賠償額を予定したもの」である場合もあれば、損害賠償とは別に払うべき「制裁としての金銭(違約罰)」である場合もあるのです。
少しややこしいところですので、もう少し説明します。
損害賠償額の予定としての違約金
そもそも、契約の違反があれば、違反した側は、これによって相手方が被った損害を賠償する義務を負います。
契約書でもこうした損害賠償義務が記載された条項がある場合が多いですが、たとえ、契約書にそのような記載がなくても、民法の一般原則によって上記のような損害賠償義務が認められます。
もっとも、損害賠償を請求する側は、実際に賠償請求をする場面では、契約違反によって損害が発生したことや、具体的な損害額を立証する必要があり、実は、これがなかなか容易なことではありません。
具体的な損害の立証が難しいために、契約違反があることは明らかでも損害賠償請求することが出来ないという状況が生じてしまうのです。
そこで、あらかじめ契約書で損害賠償の予定額を定めておき、契約の違反があれば、具体的にそれによっていくらの損害が発生したかを立証しなくても、予定された金額を請求できるようにしておくことができます。これを「損害賠償額の予定」といいます。
例えば、損害賠償額の予定として、「100万円」とあらかじめ定められていると、契約違反によって損害が発生したことや、その額を立証しなくても、契約違反の事実さえあれば、あらかじめ定めた100万円の損害賠償請求が出来るのです。
違約罰としての違約金
以上で説明したような「損賠償額の予定」とは異なり、損害賠償とは別に払うべき「制裁としての金銭」として違約金を定めている場合があります。これを「違約罰」といいます。
例えば、違約罰として100万円が定められていると、契約違反があった場合には、違約罰として100万円を請求するとともに、これとは別に実際に被った損害(例えば200万円の損害が発生しているのであれば、200万円)の賠償請求ができることとなるのです。
このように違約金が定められている場合には、それが損害賠償額の予定なのか、違約罰なのかによって、請求できる金額(請求される金額)が大きく変わってきます。そのため、両者をきちんと区別して、その意味を把握することが重要となります。
「損害賠償額の予定」の推定
フランチャイズ契約書によっては、単に「違約金」と書いてあるだけで、その趣旨がはっきりしない場合もあります。
この点、民法では、違約金は「賠償額の予定と推定する」と定められています(民法420条3項)。
したがって、違約金の趣旨がはっきりしない場合には「賠償額の予定」と考えることとなります。
「損害賠償額の予定」か「違約罰」かを巡るトラブル
フランチャイズ契約書の記載が曖昧ですと、違約金の趣旨を巡ってトラブルが生じます。
例えば、平成27年12月22日東京地裁判決は、フランチャイジーによる商標の使用違反による違約金が問題となった事例です。
このケースでは、契約書には、契約違反があった場合には「少なくても違約金として、違反が発生した直近月のロイヤリティの24ヶ月分を甲(フランチャイザー)に対して支払うものとする。当該違約金は、甲から乙への損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではない。」と記載されていました。
この規定では、ロイヤリティ24ヶ月分の請求については「損害賠償額の予定」のようにも読めますし、「違約罰」(つまり、これとは別に損害賠償請求もできる)のようにも読めます。そのため、果たして「損害賠償額の予定」なのか、「違約罰」なのかが争われました。
裁判所は、
当該違約金条項が、違約金の額を「少なくても」ロイヤリティの24か月分とし、これを超える額の違約金が発生する場合があり得ることを前提としていることに照らせば、当該違約金条項は損害の有無にかかわらず直近のロイヤリティの24か月分を損害賠償額と定めた損害賠償額の予定(ただし、これを上回る損害が生じた場合にはその額を基準として損害賠償の請求をすることができる)を定める旨の条項と理解するのが自然
として、これを「損害賠償の予定」と結論づけました。
そして、24ヶ月分のロイヤリティ相当額の請求とは別に行ったフランチャイザーからの損害賠償請求については、これを認めなかったのです。
「損害賠償の予定」の適用範囲を限定的に捉えた裁判例
「損害賠償の予定」と考える場合でも、その意味を限定的に捉える裁判例(平成19年7月19日福岡高裁判決)もあります。
この事案では、フランチャイズ契約において、契約の条項に違反した場合には、違約金として「500万円又は相当額」を支払うこととされていました。
裁判所は、この文言からすると、この約定は、(契約の条項に違反した場合一般を対象としているのではなく)契約違反のうち、一定の範囲のものについては損害賠償額(500万円)の予定を定めたものであり、それ以外については、一般の債務不履行責任によることを確認的に規定したものに過ぎないと考えるべきであるとしました。
そして、具体的には、損害賠償額が500万円と高額であること等から、この部分が適用されるのは、本件契約に違反する行為のうち,契約終了後の商標の無断使用による営業継続など、「契約違反の内容がフランチャイザーのフランチャイズ事業の根幹を揺るがすおそれがある場合に限られる」としました。
このように「損害賠償の予定」と考える場合でも、規定の仕方や金額によっては、文字通りどのような契約違反であっても、その金額を請求できるとは限らない場合がある点に注意が必要です。
違約罰と公序良俗違反
違約罰であれ、損害賠償額の予定であれ、そこで定められた金額があまりにも高額な場合などには、規定自体が公序良俗違反となりえます。
例えば、平成18年7月25日東京地裁判決は、金券ショップのフランチャイズ契約の終了に伴う保証金の返還請求等が問題となった事案です。
この事案のフランチャイズ契約では、フランチャイジーに契約違反があり、フランチャイザーからフランチャイズ契約を解除された場合には、加盟時に預託した店舗保証金等600万円の返金を受けられない旨が規定されていました。
問題になったフランチャイジー(加盟店)の契約違反は、フランチャイザーが商品管理を行うコンピュータを通さずに商品を買い取り販売をしていたという行為でした。
裁判所は、この規定は違約罰を定めた規定であるとした上で、これが公序良俗に反するかどうかは、
契約内容、原告(フランチャイジー)の債務不履行の態様・期間、被告(フランチャイザー)に与えた損害、債務者の不利益の内容等を総合的に検討すべきである
としました。
そして、本件では
- フランチャイジーの債務不履行の程度は軽微なものとはいえないが,その違反期間が3か月程度であること
- フランチャイジーの債務不履行により、フランチャイザーが被った具体的な損害はないこと
- 違約罰の規定が有効となることにより被るフランチャイジーの不利益は大きいこと
- そもそも本件の保証金を没収する合理的理由がないこと
- 違約罰としての金額がロイヤリティに換算すると月額120か月分という莫大な金額であること
- 他方、フラチャイジーは、月額10万円程度の利益を得ていたのに,さらなる利益を得るために違反を行ったのであり、違反がなければ、本件契約は継続し、フランチャイジーは、フランチャイザーに対し、残存契約期間約50か月のロイヤリティを支払ったものと解されること
等の事情を指摘して、違約罰を定めた本件規定については、ロイヤリティの50か月分250万円を超える部分については、公序良俗に反し無効と解することが相当である
と結論付けました。
違約金が無効とされた事例については、高額すぎる違約金の効力でも紹介しています。
まとめ
これまで見てきたように、フランチャイズ契約に違約金の定めがある場合にも、その意味内容は様々です。
そのため、契約違反があることが明らかでも、実際に、これに基づいてどのような請求が可能か(請求を受けるか)については、慎重な検討が必要となります。特に、違約金の金額が不合理に高すぎる場合には、公序良俗違反として請求が一部しか認められない可能性も出てきます。
したがって、フランチャイズ契約を締結するとき、あるいは、実際にトラブルが生じてしまった場面等では、こういった観点から違約金条項についてよく検討し、必要に応じて弁護士にご相談頂ければと思います。
フランチャイズトラブルでお悩みの方へ
フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。
トラブルを未然に防ぐためにも、また発生してしまったトラブルに的確に対応するためにも、早めのご相談が大切です。
フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。
あわせて読むと理解が深まる記事
さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。
▼フランチャイズ損害賠償|説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法
逆に加盟店からの損害賠償請求を考える場合もありますが、その根拠となりうる情報提供義務違反について解説しています。
▼【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策
違約金トラブルが生じる場面では、契約終了後の競業避止義務についてもあわせて問題となることが少なくありません。
▼フランチャイズの解約・脱退方法は?
フランチャイズ契約の終了のさせ方について解説しています。