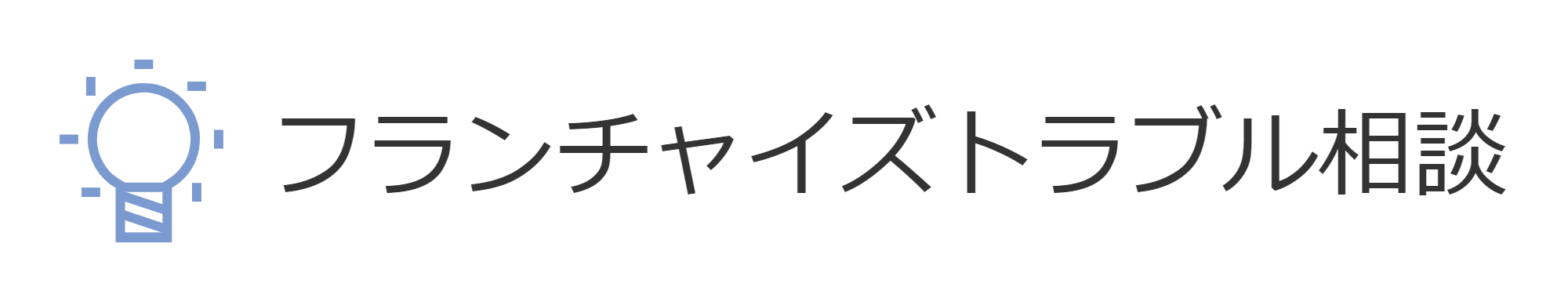フランチャイズ契約の解約・終了時に問題となる競業避止義務
フランチャイズに加盟していても、「もうこのまま続けるのは難しい」「本部の方針と合わなくなってきた」「独自ブランドで勝負してみたい」と感じることは決して珍しくありません。
経営の方向性の違いやロイヤリティ負担、人材・仕入れの制約など、契約を続けるうえでの悩みは多くの加盟店が抱えています。
こうした事情からフランチャイズ契約の終了を選択した場合に、契約を終了させたあとも、これまでの経験やノウハウ、人脈を活かして同じ業種で再出発したいと考えるのは、自然な流れでしょう。
しかし、ここで注意しなければならないのが、「競業避止義務」と呼ばれるフランチャイズによくある制約です。
フランチャイズ契約が終了すれば、契約に伴うすべての義務から解放されるように思うかもしれませんが、実際には、契約終了後も、いくつかの義務については制約が続きます。その代表例が、この「競業避止義務」です。
この義務に違反して営業を始めてしまうと、フランチャイズ本部から損害賠償請求や営業差止請求の訴訟を起こされるリスクがあります。この点を理解せずに独立や転業を進めてしまうと、せっかくの再出発が法的トラブルに発展しかねません。
本記事では、フランチャイズ契約終了後に問題となる競業避止義務について、競業避止義務の基本的な仕組み・有効と無効を分ける判断基準・裁判例から見る傾向・違反時のリスクとそれを回避緩和するための対応を体系的に解説します。
「もう契約を終えたい」「同じ業種で独立したい」と考える加盟店にとって、安全に次の一歩を踏み出すための指針として役立てていただければと思います。
競業避止義務とは?基本的な法的仕組み
競業避止義務の定義と目的
「競業避止義務」とは、フランチャイズ加盟店が、契約期間中または契約終了後に、本部と同一または類似の事業を行ってはならない義務のことをいいます。
多くのフランチャイズ契約書には、次のような条項が定められています。
契約終了後○年間は、同一または類似の事業を営んではならない
競業避止義務は、フランチャイズ契約に限らず、雇用契約や業務委託契約などでも問題となりますが、フランチャイズ契約では契約書に明確に規定されていることが多く、実務上も争点となりやすい条項の一つです。
フランチャイズ本部(フランチャイザー)は加盟店(フランチャイジー)に対して、営業ノウハウや商標、経営指導などを提供し、加盟店は本部のブランド力や経営システムを利用して事業を行います。
しかし、契約期間中はもちろん、契約が終了した後に、加盟店が同じ場所や地域で同じような事業を始めた場合、
- 本部の営業秘密やノウハウが流出する
- 商標やブランドの信用が損なわれる
- 既存加盟店や本部の商圏が侵害される
といった不利益が生じかねません。
このような事態を防ぐために、フランチャイズ契約では「契約終了後○年間は同一業種の営業をしてはならない」といった条項を設け、本部の正当な利益を保護し、フランチャイズシステムの安定的な運営を維持するために競業避止義務が設定されています。
法的根拠:契約による合意とその限界
このように契約終了後の競業避止義務は、フランチャイズ本部と加盟店との契約(合意)に基づいて発生します。
しかし、契約であればどのような内容でも自由に定められるわけではありません。
競業避止義務の範囲があまりに広すぎると、加盟店にとっては契約終了後に行うことができる仕事が著しく制限され、憲法上の権利でもある職業選択の自由や営業の自由を過度に制約することになります。
とりわけ加盟店が多額の設備投資を行っているような場合には、投下資本の回収が妨げられるという重大な結果をもたらします。
そのため、加盟店の職業選択の自由や営業の自由を過度に制約する競業避止義務の定めは、公序良俗に違反するものとして、法的には無効となる場合があります。
具体的には、次のような要素が重なるほど、無効と判断されやすくなります
- 禁止期間が長すぎる
- 禁止地域が広範囲すぎる
- 対象業種が曖昧または過剰に広い
また、多くのフランチャイズ契約では、競業避止義務に違反した場合の違約金が定められていますが、その違約金が過大な場合も問題となります。たとえ競業避止義務自体が有効であっても、違約金の金額が過大であれば、その部分のみ効力が制限されることもあります。(詳しくは、フランチャイズ契約の競業避止義務と違約金:無効となるケースと裁判所の判断基準で、解説しています)
独占禁止法との関係
フランチャイズ契約における競業避止義務は、契約上の問題にとどまらず、独占禁止法の観点からも問題となります。
内容によっては、フランチャイズ本部による加盟店の事業活動の自由を不当に制限するものとして、「不公正な取引方法」や「優越的地位の濫用」に該当する可能性があるためです。
たとえば、契約終了後に数年間、広範囲な地域で競業を禁止するような条項は、加盟店の営業の自由を過度に制限するものとして独占禁止法上問題となる可能性があります。
(▼詳しくは「フランチャイズ契約の競業避止義務と独占禁止法」で、ガイドラインや判断基準を解説しています)
まずは契約書を確認
以上のように、契約終了後の競業避止義務は本部と加盟店との間の契約(合意)に基づいて生じますが、無限定に認められるわけではありません。
そのため、契約終了を検討する段階では、まずはフランチャイズ契約書において契約終了後の競業避止義務がどのように定められているのか確認することが重要です。そのうえで、その効力やリスクを客観的に見極めていく必要があります。
有効性の判断基準
競業避止義務条項の有効性の判断基準について、裁判例も踏まえてもう少し詳しく見ていきます。
判断の基本枠組み
競業避止義務の有効性は、本部(フランチャイザー)の保護すべき利益と加盟店(フランチャイジー)の営業・職業選択の自由とのバランスで判断されます。
裁判例では、主に次のような点を総合的に考慮して、有効か無効かを判断しています。
- 目的が正当か(ノウハウ保護・商圏維持など)
- 禁止期間・地域・業種の範囲が合理的か
- 加盟店が被る経済的不利益が過度でないか
- 契約終了の経緯(どちらに責任があるか)
これらの点を踏まえ、「フランチャイズ本部の正当な利益を守るために必要かつ合理的な範囲内の制限かどうか」という観点から判断されます。
無効と判断された裁判例
たとえば、ある労働者派遣業のフランチャイズ契約をめぐる裁判(東京地裁平成21年3月9日判決)では、フランチャイジーが契約終了後も関連会社を通じて同種の派遣事業を続けたため、本部が競業避止義務違反を主張して訴訟を提起しました。
裁判所は、確かに競業行為に該当するとしながらも、以下の事情を踏まえて、「競業禁止により保護されるフランチャイザーの利益が、競業禁止によって被る旧フランチャイジーの不利益との対比において、社会通念上是認しがたい程度に達している」として、この競業避止義務を公序良俗違反により無効と判断しました。
・本部の商圏が実質的に存在していなかったこと
・提供されたノウハウも契約終了時点では秘密性・有用性を欠いていたこと
・競業避止規定により廃業以外の選択肢がなく、しかも、廃業に伴う対価を得られる見込みがなかったこと
・契約終了に至る経緯には本部側の事情も大きく影響していたこと
有効と判断された裁判例
一方で、高齢者向け弁当宅配のフランチャイズ契約に関する裁判(大阪地裁平成22年1月25日判決)では、契約終了後に同一店舗で同様の事業を継続した加盟店に対して、本部が差止めと損害金支払いを求めました。
この裁判で裁判所は、以下の点などを指摘して、制限の目的や範囲は合理的であり、営業の自由を過度に制約するものではないとして、競業避止義務を有効と認めました。
・同業他社との差別化ができている本部のノウハウの流用防止の観点から、規定の趣旨目的に合理性があること
・禁止期間が3年、地域も旧営業エリアに限られていたこと
(▼これらの 裁判例の詳細は「フランチャイズ契約の競業避止義務は有効?無効?裁判例から学ぶ判断基準」の記事で紹介しています)
違反するとどうなる?損害賠償と差し止めリスク
競業避止義務に違反すると、次のような法的措置や経済的損失を被るおそれがあります。
- 営業差止請求:営業の停止を余儀なくされる(⇒詳しくは、フランチャイズ契約における競業避止義務違反を理由とする業務差し止めが認められる場合)
- 損害賠償請求:契約で定められた違約金、または実際に発生した損害の賠償を求められる
いきなり裁判を起こされるケースもありますが、多くの場合は、まずは弁護士を通じて警告や請求が送られてきます。フランチャイズ本部にとっても、訴訟はコストや労力がかかるため、まずは話し合いによる解決を目指すのが一般的です。
ただし、交渉で解決出来ない場合には、裁判で決着が図られることになります。旧加盟店側としては、こうした請求や訴訟に対応しなければならないということ自体、一つのリスクと言えます。
こんな点にも注意!競業避止義務にまつわる論点
競業避止義務については、これまで見てきたように「有効か否か」という大きな問題がありますが、それ以外にも次のような点も問題となります。
①当事者以外にも効力が及ぶか
競業避止義務は、原則としてフランチャイズ契約を結んだ当事者同士──つまり本部と加盟店の間でのみ効力を持ちます。しかし、実際には家族や別会社、従業員などの第三者が関わるケースでも、問題となることがあります。
たとえば、加盟店本人が脱退後に新会社を設立して同じ業種を続けた場合や、家族・元従業員が実質的に同じ店舗を引き継いだ場合などです。こうしたケースでは、「形式的には別の主体」でも、実質的に同じ人が事業を継続していると判断されれば、契約当事者と同様に競業避止義務の対象とされる可能性があります。
実際の裁判でも、加盟店本人が100%出資して代表を務める法人を設立した場合や、加盟店の従業員が実質的に店舗を引き継いだ場合に、「信義則上」競業禁止の対象に含まれると判断された例があります。
つまり、名義を変えたり法人を介したりしても、「実質的に本人が関与している」と見なされると、競業避止義務から逃れられないことがあるのです。
(▼ 詳しくは「当事者以外の者も競業禁止義務の対象となるか」で解説しています。)
② 譲渡行為が禁止の対象となるか
契約終了後に、店舗や設備、顧客を別の会社に引き継ぐような形で事業を譲渡する場合、それが「競業避止義務に違反するのではないか」と問題になることがあります。
たとえば、加盟店がフランチャイズ契約を終了した後に、別のフランチャイズ・チェーンに店舗設備を売却したり、顧客やスタッフを引き継ぐような形で新しい事業を始めるケースです。このような場合に、「第三者に営業をさせた」として違反を主張されることがあります。
こうした点が争われたある裁判例では、加盟店が什器や設備を別会社に売却しただけであり、顧客リストやノウハウを提供したわけではなかったことから、「第三者に営業をさせた」とまではいえず、競業避止義務違反は認められないとされました。
ただし、これはフランチャイズ契約で明示的に禁止されていなかったケースですので、契約書にどう記載されているのかの確認がやはり出発点として重要です。
(▼詳しくは「競業避止義務によってどの範囲の行為が許されなくなるかが争われた事例」で解説しています)
③ 信義則によって制限される場合
契約書上の競業避止義務が有効と判断される場合でも、本部と加盟店の事情や経緯によっては、その適用が信義則上制限されることがあります。
実際の裁判では、加盟店が本部からの不十分な情報提供により多額の初期投資をしたにもかかわらず、契約終了後に競業を禁止されてしまうのはあまりに酷だとして、「信義則上、競業避止義務を適用できない」と判断された例があります。
このように、条項そのものが有効でも、加盟店が多額の費用を投じており回収の見込みがない、その投資を行うに至った原因が本部側の説明不足などにある、といった事情がある場合には、裁判所が競業避止義務の適用を否定することもあるのです。
(▼詳しくは「競業避止義務違反が信義則上否定された裁判例」で、実際の事案と裁判所の判断を紹介しています。)
④ 何が「競業行為」に当たるか
契約書に「同業種の営業をしてはならない」と書かれていても、実際にどのような事業を行っているかによって、競業に当たるかどうかの判断は分かれます。
たとえば、デンタルエステのフランチャイズを脱退した加盟店が、一般的な歯科診療やホワイトニングを続けたケースでは、本部は「競合する事業だ」と主張しましたが、裁判所は、加盟店の提供していたサービス内容がフランチャイズ本部の提供していた「エステ的メニュー」や経営ノウハウとは異なるとして、競業には当たらないと判断しました。
このように、競業避止義務の範囲は契約書の文言だけでなく、事業の実態に基づいて判断されます。
単に「同業だから禁止される」とは限らず、実際のサービス内容・経営手法・顧客層などを総合的に比較して決められるのです。
契約書の文言が広く書かれている場合でも、実際の事業が本部のノウハウやブランドを利用していないのであれば、競業に当たらないと判断されることもあります。
トラブルを防ぐためにできること ― 契約終了前後の実務対応
フランチャイズ契約を終了させるとき、競業避止義務に関するトラブルを防ぐ最大のポイントは、「契約書の条項を正確に理解し、行動前に確認を済ませておくこと」です。
ここでは、実務上注意すべきステップを整理します。
1.まずは契約書を確認する
競業避止義務に関する定めといっても、フランチャイズごとに様々な内容になっています。契約書の文言上、どのように書かれているかは出発点として非常に大切となります。次の点を中心に確認しておきましょう。
- 禁止されている行為の範囲:同一事業・類似事業など、どこまでが禁止されているか
- 禁止期間:何年間・どの時点から起算するのか
- 禁止地域:店舗所在地のみか、都道府県単位か
- 違反時のペナルティ:違約金や損害賠償の定めがあるか
違約金については、他の義務違反とあわせて別の条項に記載されていることも多くありますので、こちらも忘れずにチェックして下さい。
2.「名義を変えれば大丈夫」は危険
「法人名義なら問題ない」「家族の名義でやれば大丈夫」と安易に考えるのは危険です。
先に見たとおり、形式面だけを整えても、実質的に本人が関与していると判断されれば、競業避止義務違反と認定される可能性があります。
したがって疑義が生ずるようなケースでは、実質的な中身も含めて丁寧な事業設計を行うことが重要となります。
3.設備・顧客・スタッフの引継ぎにも注意
店舗や機器、顧客リストを別の会社に引き継ぐ場合も、競業避止義務との関係で問題となることがあります。
譲渡や移転を行う際は、契約書上の「営業譲渡」「再加盟禁止」条項との関係や、実際の引継ぎ範囲(物的・人的・情報的要素)を慎重に確認し、場合によっては法的リスクを評価してから実施するべきです。
4.契約終了の原因も重要
競業避止義務の効力の判断や適用にあたっては、契約終了の経緯も影響します。
本部側に問題があって契約が終了するようなケースまで、競業避止義務による制約を認める必要があるのかという判断があるからです。その意味では、どのような形で契約を終了させるのかも一つのポイントとなります。
フランチャイズ契約を終了させるということは、基本的には、加盟店としては、本部側の対応等に満足をしていないからでしょう。その不満が、何らかの義務違反など法的な問題にならないのかといった点の検討も必要です。
例えば、よく問題となるのは、「加盟前に聞いていた話と全く違う」という不満ですが、これが本部側の情報提供義務違反という法的な問題となる場合もあります。
(▼情報提供義務違反について詳しくは、「フランチャイズ損害賠償|説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法」で解説しています)
契約終了までにトラブルがあったり、主張に食い違いがあるようなケースでは、本部とのやり取り(メール・通知書・打合議事録など)をできる限り保存しておきましょう。後に「どちらに責任があったのか」を立証する重要な資料となります。
5.疑問点は早めに弁護士に相談を
競業避止義務の有効性や範囲は、条文だけで判断するのは困難です。また、「どこまでが競業に当たるのか」「名義を変えた場合はどうか」といった問題は、具体的な事情によって判断が分かれます。
安易に考えて後で「しまった!」となることのないように、迷った場合には、早めに弁護士に相談して、慎重にリスクの見極めと対策を行うことが大切になります。
まとめ
これまで見てきたように、フランチャイズ契約が終了しても、多くの場合は競業避止義務が定められており、違反すれば営業の差止めや損害賠償請求を受けるリスクがあります。
もっとも、その制約が過度に大きい場合には、職業選択の自由を不当に制約するものとして無効と判断されることもあります。
したがって、契約を終了して独立や転業を考える際は、まずは契約書の競業避止条項を確認し、**「どの範囲までが禁止されているのか」「その制限は妥当か」**を慎重に見極めることが重要です。疑問がある場合には、早めに弁護士へ相談し、リスクを把握したうえで安全に次の一歩を踏み出しましょう。
フランチャイズトラブルでお悩みの方へ
フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。
トラブルを未然に防ぐためにも、また発生してしまったトラブルに的確に対応するためにも、早めのご相談が大切です。
フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。
あわせて読むと理解が深まる記事
さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。
▼フランチャイズの解約・脱退方法は?
加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。
▼フランチャイズ契約と加盟金の返還請求
「加盟金は返還しません」という合意の効力について解説しています。
▼フランチャイズの違約金は払わないといけない?拒否できる場合と裁判例を解説
解約時によく問題となる違約金の問題について解説しています。