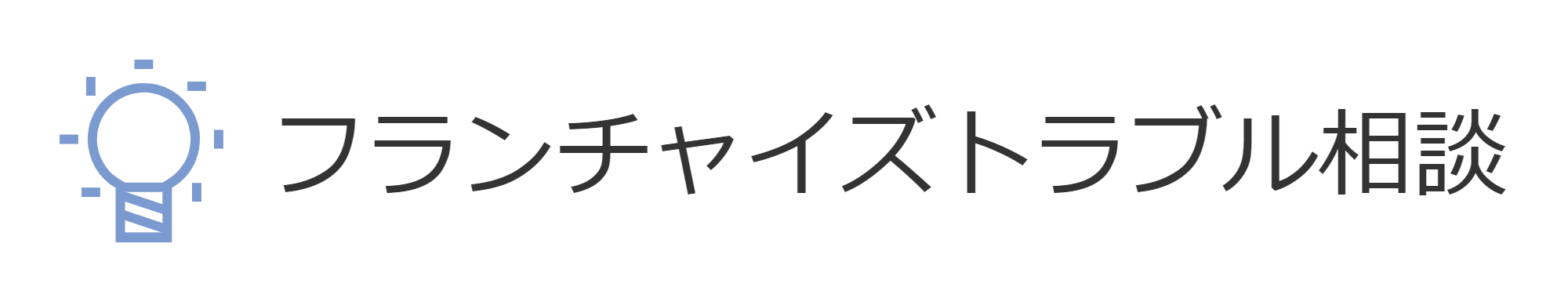相談者
相談者自分はフランチャイズ加盟店ですが、フランチャイズ契約の「競業避止義務」には以前から納得がいきません。契約が終わった後も、しばらくは同じような商売ができないというのは、あまりに厳しすぎると思うのですが。独占禁止法違反とかにはならないんですか?



おっしゃる通り、フランチャイズ契約における競業避止義務は、独占禁止法との関係で難しい問題があります。結論から言うと、常に独占禁止法に抵触するわけではありませんが、その内容によっては問題となる可能性があります。



「内容による」ですか。具体的にどういう場合に問題になるんですか?



はい。独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進することを目的としています。競業避止義務のような、事業活動を制限する契約は、その本質上、競争を阻害する可能性を秘めているため、細かくチェックされるんです。
公正取引委員会は、フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方として、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」というものを公表しています。
このガイドラインでは、競業避止義務が独占禁止法上の問題となり得るかどうかを判断する際の基準が具体的に示されています。



どういう基準が示されているんですか?



ガイドラインでは、競業避止義務の目的、期間、地域、対象事業の範囲などが総合的に考慮されます。
まず、競業避止義務の「目的」です。フランチャイズ契約における競業避止義務は、本部のノウハウやブランドイメージといった「フランチャイズ・システムの維持・保護」が正当な目的とされます。
なので、加盟店が契約期間中や契約終了直後に、本部から得たノウハウを使って競合店を出したり、加盟店同士で顧客を奪い合ったりすることを防ぐため、という目的であれば、ある程度は許容されるわけです。



なるほど、本部のノウハウを守るため、ということですね。じゃあ、期間や地域、対象事業の範囲についてはどうですか?



期間も重要ですね。 競業避止義務が課される期間が不当に長すぎる場合は問題となります。
ガイドラインでは、原則として契約終了後1年以内であれば問題となりにくいとされています。もちろん、事業の内容やノウハウの特殊性によっては、例外的に1年を超える期間が認められる場合もありますが、それでも数年といった長期にわたる場合は、正当性が厳しく問われることになります。



競業を禁止する「地域」の範囲が不当に広すぎる場合も問題です。
例えば、加盟店の営業区域をはるかに超えた広範囲な地域で競業を禁止することは、加盟店の事業活動の自由を過度に制限し、独占禁止法上の問題となる可能性があります。加盟店が実際に営業を行っていた地域や、本部の顧客基盤が及ぶ合理的範囲に限定されるべき、と考えるのが一般的です。



禁止される「対象事業」の範囲が不当に広すぎる場合も問題となり得ます。例えば、フランチャイズ契約で喫茶店を経営していた加盟店に対し、契約終了後に「飲食業全般」を禁止するなど、提供していたサービスと直接競合しない事業まで広範に禁止することは、過度な制限とみなされる可能性があります。フランチャイズ・システムの保護に必要な最小限の範囲に限定されるべきです。



期間や地域、対象事業の範囲がポイントなんですね。もし、これらが「不当に広い」と判断されたらどうなるんですか?



その場合、その競業避止義務条項が独占禁止法に違反すると判断される可能性があります。独占禁止法違反と認定されれば、その条項自体が無効となったり、公正取引委員会からの排除措置命令や課徴金納付命令の対象となったりする可能性もあります。
また、仮に公正取引委員会が動かなくても、加盟店側が「この競業避止義務は不当だ」として訴訟を起こし、裁判所で無効と判断されることもあります。実際に、裁判例では、期間や地域が広すぎると判断され、競業避止義務が無効とされたケースも存在します。
競業避止義務をめぐる裁判や、終了時に加盟店がとるべき対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉 【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策



そうなると、加盟店としては、契約する前に弁護士さんにチェックしてもらうのが本当に大事なんですね。



その通りです。まさにそれが失敗を回避するための最も重要なポイントです。
フランチャイズ契約書や、契約前に交付される「法定開示書面」には、これらの競業避止義務に関する条項が必ず記載されています。これを加盟店ご自身だけで判断するのは非常に困難です。
弁護士は、フランチャイズ・ガイドラインや過去の裁判例に照らして、その競業避止義務条項が適正な範囲内にあるか、あるいは独占禁止法に抵触する可能性がないかを詳細にチェックすることができます。もし問題があるようであれば、本部に対して条項の修正を交渉する支援も可能です。



契約前に弁護士に相談せず、そのまま契約してしまった場合はどうなりますか?後からでも対処できますか?



うーん・・・。 契約してしまった後でも、対処が全く不可能というわけではありません。契約締結後に「やはりこの競業避止義務はおかしい」と感じた場合、弁護士に相談して法的有効性を争うことは可能です。
ただし、契約前にしっかり確認しなかったという不利な立場からスタートすることになりますし、交渉や訴訟には時間も費用もかかります。そのため、トラブルが顕在化する前の「予防」が何よりも重要なのです。契約書にサインする前の段階でのリーガルチェックは、後の大きなトラブルを未然に防ぐための「投資」だと考えていただくと良いでしょう。



弁護士さん、今日のお話で、フランチャイズ契約の競業避止義務が思っていた以上に複雑で、独占禁止法との関係もしっかり考えないといけないことがよく分かりました。ありがとうございます。



どういたしまして。フランチャイズ加盟は大きな決断です。皆様が安心して事業に取り組めるよう、法的リスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが成功への第一歩となります。何かご不明な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
フランチャイズトラブルでお悩みの方へ
フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。
トラブルを未然に防ぐためにも、また発生してしまったトラブルに的確に対応するためにも、早めのご相談が大切です。
フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。
あわせて読むと理解が深まる記事
競業避止義務についてさらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。
▼【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策
競業避止義務の基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを体系的に解説しています。
▼フランチャイズの解約・脱退方法は?
加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。
▼フランチャイズと独占禁止法
フランチャイズ契約において独占禁止法違反が問題となる様々な場面について解説しています。