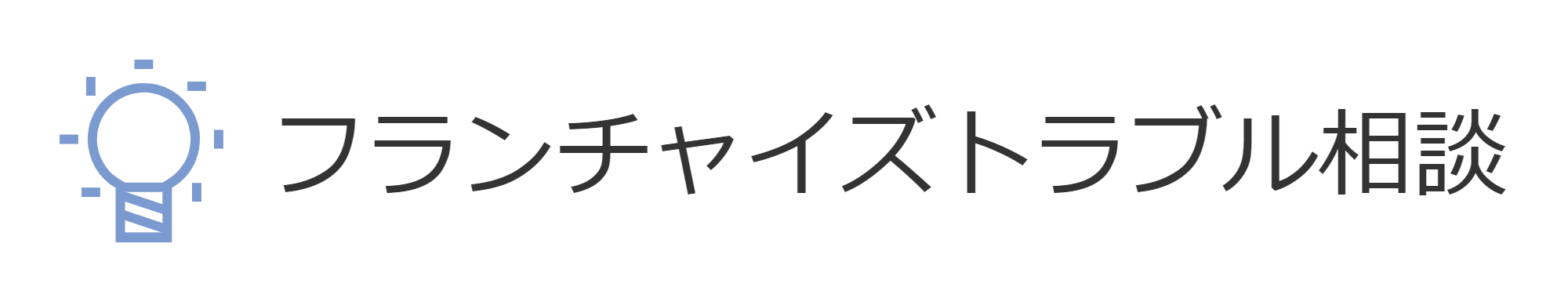フランチャイズ契約では、加盟店(フランチャイジー)にとって本部(フランチャイザー)の指示が不当であっても、その立場の違いから、加盟店が泣く泣く本部の指示に従ってしまう場合があるかと思います。
今回は、このような場合のうち、本部による加盟店への見切り販売制限が、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたると判断された事例(平成21年6月22日公取委命令)について、ご紹介します。
なお、フランチャイズ契約において独占禁止法違反が問題となる様々な場面についてはフランチャイズと独占禁止法で解説しています。
事案の概要
この事例では、あるコンビニエンスストア本部が加盟店に対し、廃棄される商品の原価相当額の全額が加盟者の負担となる仕組みの下で、見切り販売を行わないようにさせる、見切り販売を取りやめないときは基本契約の解除等の不利益な取扱をする旨を示唆するなどして、見切り販売の取りやめを余儀なくさせていました。
そこで、上記本部の対応、すなわち、見切り販売を制限する対応が「優越的地位の濫用」にあたるかが、問題となりました。
公正取引委員会の判断
優越的地位にあたるか
まず、本部が「優越的地位」にあたるかについて、
①店舗数直営店約800店、加盟店約1万1200店を抱える最大手のコンビニ・チェーン事業者である本部に対し、加盟店のほとんど全てが中小の小売り事業者であること
②基本契約期間が15年で、契約終了後、加盟者が自ら用意した店舗でコンビニエンスストアを経営する場合、契約終了後1年間は他のコンビニ・チェーンに加盟できないこと
③加盟店で販売される商品のほとんど全てが推奨商品となっていること
④加盟者は、本部管理下の経営相談員の指導・援助に従って経営を行っていること
との事情を挙げて、「優越的地位」にあたることを認定しています。
この判断は、フランチャイズ・ガイドラインにおいて判断要素とされている加盟者の本部に対する取引依存度(①、③、④)、本部の市場における地位(③)、加盟者の取引先の変更可能性(②)、本部及び加盟者間の事業規模の格差(①)に対応した判断といえます。
濫用にあたるか
続いて、見切り販売の制限が「濫用」にあたるかについては、
ⅰ 本部が収受するロイヤルティの額は加盟店で廃棄された商品の原価相当額の多寡に左右されないこと
ⅱ 廃棄された商品の原価相当額が加盟者の全額負担となっていること
を認定した上で、この事例では基本契約上販売価格を加盟者が決定することになっており、見切り販売は本来加盟者の自由であるはずにもかかわらず、これを制限したため、加盟者が合理的な経営判断に基づいて上記ⅰ及びⅱの負担を軽減する機会を失わせたことから、「濫用」にあたるとされています。
フランチャイズガイドラインにおいて、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合は「濫用」にあたるとされており、上記負担軽減の機会喪失が加盟者に不当な不利益を与えたと判断されたといえます。
今回の事例では、以上の判断から、本部の見切り販売の制限が「優越的地位の濫用」にあたるとされて、公正取引委員会から排除措置命令が出されました。
フランチャイズトラブルでお悩みの方へ
フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。
トラブルを未然に防ぐためにも、また発生してしまったトラブルに的確に対応するためにも、早めのご相談が大切です。
フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。
あわせて読むと理解が深まる記事
さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。
▼フランチャイズと独占禁止法
フランチャイズ契約において独占禁止法違反が問題となる様々な場面について解説しています。
▼フランチャイズ損害賠償|説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法
誤った情報提供が行われた場合に問題となる情報提供義務違反について解説しています。
▼【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策
競業避止義務の基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを体系的に解説しています。
▼フランチャイズの違約金は払わないといけない?拒否できる場合と裁判例を解説
高すぎる違約金が公序良俗違反となる場合について解説しています。